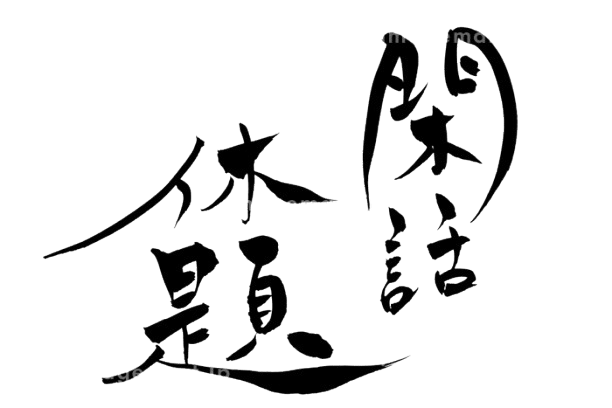令和七年 夏の日 鎌倉回想
鎌倉楽しむ会-令和7年-夏の日-鎌倉回想-②-7:8;20暑中お見舞い申し上げます。 令和7年盛夏
鎌倉楽しむ会 暑中お見舞い申し上げます 7:7:1「鯉のぼり」「母の日」
鎌倉楽しむ会 閑話「鯉のぼり」「母の日」ご挨拶
鎌倉楽しむ会の皆様
本日3月16日(日)は、思いの外の氷雨でした。桜の蕾もそろそろと開花の準備に追われていることの この寒さチョット足踏みですかね!
皆様におかれましては 益々のご健勝のこととお慶び申し上げます。
毎々大変なるご協力いただき御礼申し上げます。
ここんところNHK大河ドラマ「べらぼう」を見損なっていましたが、本日BSの午後6時から観ました。相変わらず映像は綺麗ですが、今日は、私の目には、少し中弛みのように映りました。
この大河ドラマの次に「北の英雄 阿弖流為伝」が放映され、エ~と観てしまいました。
想えば一昨年「奥州藤原王国」のお話をさせていただいた時に、「坂上田村麻呂」との戦いと講和で、この「阿弖流為」は京都まで連れていかれ、残念ながら講和が不調となり、そして斬首されてしまう。
そして現在は、坂上田村麻呂の創建と伝わる 京東山の「清水寺」の境内に「供養塔」として祀られている ということをお話したことが蘇ってつい、懐かしさもあって、2012年のアーカイブですが、興味とお時間のある方はご覧になっていただければと思った次第です。
春彼岸も間近です。お身体重々ご自愛なさりご活躍くださるよう願っております。
(清藤孝 記)
◇忙中閑話(sweet)のコーナーです
サミュエル・ウルマン「青春の碑」
八百年の時を超えて
―常楽寺~六国見山~明月院~円覚寺の道―
今にも降りだそうとする朝の9:30分、JR大船駅南口から散座ヶ池循環バス⑤出発所に向かう。この頃から弱い五月雨となってきた。空を見上げれば雲は流れところどころ雨雲の切れ目が見えているので、天気予報の1ミリ降雨を信じメンバーは5名(酒井さん、水野さん、海老名さん、森野さん、清藤ガイド)でバスに乗り込む。乗車して4っ目の「常楽寺」で降りる。
五月雨は弱く降り続けていましたが、参道は古都鎌倉らしい雰囲気の濃い空気が流れる茅葺の重みのある山門が静かに出迎えてくれた。縄文時代の中期辺り(BC5000)には、この辺りまで海水が入り込んでいて、掲げられている「粟船山(ぞくせんざん)」の謂れを、参加者全員が資料を見ながら語り合う面白さも倍加し境内に入りました。小雨に濡れ艶やかに輝く木々や草花、その静寂とした中に御本堂は開扉し、ご本尊阿弥陀如来様が脇侍の勢至・観音菩薩様と共に我々一行を出迎えてくれたように見えました。
ご本堂を回り込み、目的の「三代執権の北条泰時」のお墓に手を合わす。鎌倉幕府の執権制度が発足し16代の執権が名を連ねる中で、身近に一般のお参りができるのは、この三代執権泰時のお墓だけではないのだろうか❓そのような思いの中、参加のみなさんから「承久の乱」の時いち早く18騎の大将として京に向ったことや、朝夷奈切通しの開通、和賀江島の建設、御成敗式目の制定などの話がキャッチボールされ、800年前の時空を超えた楽しいひと時の場面でした。
そして、これも鎌倉らしい「文殊堂」にお参りし、次に「清水冠者義高」の供養塔に向えました。常楽寺の裏手の小高い一角にこじんまりとお花が飾られ祀られていました。11歳で人質、そして12歳で誅殺される。壮絶な権力争いの中の悲しき物語が、この目の前に歴史の証人として小雨の中に佇んでいました。
ゆっくりと30分ほどの常楽寺を見学し、多聞院に移りました。このお寺さんは大覚寺派真言宗ですが、京都のお寺さんの雰囲気をもった綺麗な景観です。小雨は依然として降り続いていましたが、この位ならこれから向かう六国見山の山道も大丈夫と感じ、親切にも「お手洗い」の案内板を掲げていた清浄ところをお借りして、隣接する熊野神社に50段位の石段を上り参拝しました。珍しいことに御祭神は「ヤマトタケル尊」でした。後北条時代に創建されたとのことですが、摂社に「金毘羅宮」があり御祭神は「崇徳上皇」でした。崇徳上皇といえば「皇位継承争いの保元の乱」に敗れ讃岐国に流された上皇ですが、ここで海老名さんから、「崇徳上皇の怨念」についての解説があり、これが本日の鎌倉散策に花を添えてくださったことでの大収穫でした。
静かな中にも威厳の漂う熊野神社の少し危険な脇階段を降り、今泉通りを横切り往時の切通しに入りました。この切通しの下は今横切った今泉通りが現在は短いトンネルになって車道となっています。鎌倉の中でも短い切通しですが往時の苦労された工事状況の痕跡があり、上り歩きながら全員が「すごいね!また、何のためこの切通しは作ったのか?」など会話がなされ「金沢・六浦から往時の鎌倉街道への物資道」ということで結論のない想像の世界の話し合いでした。
切通しを過ぎ大船高校の脇に出、坂道の住宅街を過ぎ、「高野台バス停」に出ました。高級住宅街らしく見ごたえある住宅が手入れよく見られる一方で、建物のない雑草の生えた高台の高級そうな土地もあり、維持管理の大変さが現実に見えた感じでした。
そして、ここに六国見山登り口の看板標識があり、登山(?)開始となりました。このころ(11時)小雨も止んできました。ここから一気に150段位のコンクリート階段を上ります。上りきったところから、今度はなだらかな上り山道になります。途中水分補給で一服。また少し上ると令和元年の19号台風で大木が倒され、それを整備した場所にでます。少し見晴らしが良いので大船観音も見えるそうですが、見つけられませんでした。
もうすく六国見山見晴台です。小雨もラッキー止みました!11時30分予定通り到着!。相模湾バッチリ!空気旨し!昼食開始。富士山残念!
ここに「浅間大神」のおおきな石碑あり、揮毫は円覚寺207世管長釈宗演となっています。釈宗演管長は「禅」を世界に広める尽力をされ、鈴木大拙師をアメリカに派遣し、また円覚寺の後には「東慶寺」の住持をも務められた革新的な僧侶であったということです。
いよいよ六国見山ハイキングコースから明月谷ハイキングコースの林道に入ります。
入り口で、少し早いのですが、この林道で「夏越(なごし)の祓い」をやっていこうということとなりました。「夏越の祓い」の詩に「水無月(みなづき)の夏越の祓いする人ぞ千歳(ちとせ)の命(いのち)延(のぶ)というなり」を唱え一礼して入りました。
小雨も降りそうな気配でしたが、気になる程でなく、山道も少し泥道もありましたが何事もなく下山でき、この頃には小雨もしっかりと上がっていました。方や崖、方や住宅の坂道を下り明月院通りに出ました。明月院通りは現代に入り切り開かれ10メートルはあろうかという切通しの高台のところに喫茶店が見えたり、車社会の住宅街を形成しているようです。
いよいよ明月院12時40分見学開始(拝観料500円)。各自自由に散策。境内は以前よりすご~く綺麗に整備されて案内版もしっかりと設置され、来院者の多いことを物語っているように感じ少し京風の風が吹いていました。来院者が少ない本日はラッキーでした。13時10分門前に集まり、相談の上「お茶の時間」としました。
門前の「風花」(?)さんだったと思います。おいしいコーヒーセット、抹茶セットを楽しみました。13時30分になったところで、他にお客さんも居なかったので、マスターに10分ばかりお話を伺いました。これが本日の大収穫でした。それはこの地で35年お店を開いているのですが余り詳しいことは分かりませんがという前口上でしたが、なんとなんと、明月院の住持の交代で、現在の住持さんは京都の「妙心寺」から来られた。そして境内を整えた。また、紫陽花のお話とか聞きほれるようにお話が上手く楽しい時間を20分過ごすようになり有難かったです。
明月院参観の人達が上ってくる道をチョット横道に入り、瀟洒な小路を通り「円覚寺」に向いました(入山料500円)。円覚寺山門の大きさに今更ながら感心し境内の地図を頼りに知っている範囲で塔頭の説明をして見学することとしました。向かった先は鎌倉で唯一「国宝の舎利殿」。もとは尼寺の「太平寺」で戦国時代後北条と上総国里見氏との争いで太平寺尼主が里見義弘にさらわれ、後には正室となっていく希有の世界が展開し、廃寺となり円覚寺に移築されたという謂れの国宝建築物です。次に開基された八代執権北条時宗の廟所・「佛日庵」。ここには時宗のほか9代執権貞時、14代高時も祀られていました。酒井さんから「高時は、昨年訪ねた東勝寺跡で一族郎党が鎌倉幕府陥落の時自刃してますね!」との話もだされ、また、中国の作家・魯迅が寄贈したモクレンもあり魯迅も調べてみますと探求心の旺盛なことに感心します。水野さんの知識の深さにも道々キャッチボールして、いつの日か鎌倉ガイドをお願いしようかという気になってきます。夢窓疎石の塔頭、庭園、方丈を見学、最後に「洪鐘(おおがね)」(国宝)に向えました。酒井さんは青年時代に「円覚寺の洪鐘をお正月に打たせていただいた」という話をされ、どんな素晴らしい音色を響かせたのかと想像しますとすばらしい思い出をお持ちの酒井さんと思いました。気が付いたら16時近くでした。洪鐘はパスしましたが、あらためて充実した一日を過ごさせていただいたことに感謝し、一応解散し北鎌倉駅に向えました。以上八百年の時を超えての散策レポートでした。
あとがき
今回は大失敗が一つありました。それは大船駅南口改札で9時30分スタートしましたが、集合時間を9時40分とした資料の間違えで加藤さんを取り残してしまいました。あと一分待てばと悔やまれますが、加藤さんには心からお詫び申し上げます。
しかし、今回のコースは改めて素晴らしいと思いましたので、紅葉の11月お天気に恵まれた日を選んで再チャレンジしようと思っています。宜しくお願い致します。(清藤孝 記)
京都への郷愁
時代も遠のいた昭和四十五年(1970)、日本がアメリカに続き、GNPで世界第二位となり、全国に好景気の波が押し寄せていた。
時の佐藤栄作総理は、世界に日本の経済復興が着々と進捗している姿を公開する絶好の機会と捉え、大阪吹田市の千里丘陵に、世界万国博覧会を開催した。オリンピックに間に合わせた新幹線も珍しく、これも人気の一つで、日本中が万博に湧いているような世相が漂っていた。
唯々毎日を明日の生活のため走り回っていましたが、世間の万博ブームの情報に押され、新幹線に初乗りし出かけることとしました。岡本太郎先生の度肝を貫く「太陽の塔」が強烈な印象に残る、大混雑の世界でした。宿泊は京都とし、祇園・清水寺・南座・賀茂川・等々見るものが新しく全くのお上りさんでした。
しかし、時を経て、時間的に少し余裕が持てるようになってからは、時折、過って訪れた万博の思い出は薄く、何故か京都の印象が色濃く思い出されるのです。また、京都・奈良を舞台とした小説などにも少しは触れるようになり、立原正秋先生などの絶妙な文章の情景には情感を揺さぶられ、実体験へと誘われる不思議な魅力が広がってきました。
とにかく、何も分からず京都に入り、チョット京都らしい瀟洒なお宿と思いながら、「柊屋」「炭屋旅館」など超有名なお宿は、手の届くこともなく、唯々門前を素通りし、その雰囲気をいただくことから始めました。それから、一見さんお断りやお茶をいただく作法やらを恥じを覚悟でチャレンジし、ようやくなんとなく一見さんから解放されるまで、私の感覚で漸く三年の月日を経ていたと思います。
京都に足を踏み入れてやみくもに唯々有名所を歩き回るお上りさんしました。流石京都!唖然とし訪ねては、次へと行くのですが、当時は歴史への関心が全く疎く、京都の面をせわしく巡るばかりでした。そんな中でも再訪したいと思う社寺の多さに驚くと同時に、菩提寺の総本山は、東山の浄土宗総本山知恩院という知識が、なんとなく増えてきました。
祖母の影響か、仏像への関心が少しありましたが、太秦の広隆寺に祀られる「弥勒菩薩半跏椎像」(国宝第一号)の魅力には半端ない感動を覚えたものでした。それでもまだまだお上りさんでした。
建造物では、清水寺は勿論のこと、八坂神社に魅せられ、南禅寺の「石川五右衛門」にまつわる山門、仁和寺の佇まい、妙心寺、東福寺の大きな伽藍と美しさ、唯々感心し驚くばかりでした。庭に目を向ければ竜安寺の石庭、苔寺、天竜寺の庭、さらに驚いたのは往年の大俳優・大河内伝次郎先生の庭園にはその見晴らしといい木々の彩の配置などには、ことごとく感嘆の連続でした。
また、大原の三千院、建礼門院ゆかりの寂光院、そして貴船神社や栂尾の高山寺では「鳥獣戯画」が鑑賞でき感動極まりなく、さらに橋本雅邦先生の「日蓮聖人一代記」の画集にもめぐり逢うことができその生涯の凄まじさに触れることができ、これも知らず知らずのうちにお寺を訪ねる時には、その宗派、御本尊、開基などが自 然に問い合わされるようになってきたかな?と感じできました。
また、そこからは少しずつ、建礼門院の生い立ちや、父は平清盛であり、高倉天皇の后、安徳天皇の母、そして、本格的な武家政権の誕生の前兆となる「源平の合戦」にも出逢いて、ここで、日本の中世の歴史を理解してみようと、自分では気が付かない方向にも目が向いてきたようです。
これも偶然ですが、鎌倉の地が好きで、ここも「実朝暗殺のイチョウ」の話くらいの知識でしたが、「長勝寺」という日蓮宗のお寺さんの副住職さまと出逢い、日蓮聖人のお話をいただく機会ができ、 鎌倉仏教のことなどについての勉強が高度に受けることができました。素晴らしい師匠との出逢いが始まりました。
そして、鎌倉歴史文化観光検定試験があり、これへの受験のため、また、少し知識が増えてきました。結果は平家と関連する京の都と鎌倉は切り離しての物語は成立しないということがハッキリと認識させられたことでした。例えば「清盛と頼朝」「高山寺と文覚上人」「後白河法皇と義経」「義朝と常磐御前」などの話です。
さらに、ここで一番衝撃的だったのは、頼朝と北条得宗家が、日本における武家政権を創り上げ、百五十年間君臨してきた鎌倉幕府を「足利尊氏」が主体となって倒幕してしまうということでした。
そして、この倒幕の張本人の「足利尊氏」は、私の頭では、てっきり「京の武人」としていましたが、頼朝が鎌倉幕府旗揚げにいち早く馳せ参じた「足利義兼」からの子孫であることでした。
京都を訪ねた中に「等持院」があり、足利家の菩提寺で、歴代の室町将軍の木造が安置され、その中に徳川家康公が交じっていました。この違和感も強烈に残っています。
そして、此処から、「何故?」「どうして?」という気づきが生まれきて、まだまだ「未解決の何故が?」が多く宿題としているのですが、
今回は
「足利家が何故鎌倉幕府内の勢力争いを切り抜け、
最後には、室町幕府の頂点に立てたのか?」
をテーマにして歴史探索してみました。まだまだ未熟な文章ではありますが、ご笑覧いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
江戸の地名
三幕府(鎌倉幕府 室町幕府 江戸幕府)で鎌倉は現在でも鎌倉、では江戸時代の地名が現在まであるか調べてみた。
江戸時代から残っている地名には、次のようなものがあります。
・錦糸町 江戸時代に「錦糸堀」があったことに由来し、錦糸1丁目~4丁目が地名として残っています。
・日本橋 江戸幕府の地誌書「御府内備考」には、江戸の中央として五街道の発達拠点とされていたことが記されています。
・本町 江戸にできた最初の町人町とされています
・神田 日本橋の向こうに位置し、職人町として発展した
・紺屋町、鍛冶町、鍋町、大工町、白壁町 神田周辺の旧町名です
・駿河台 家康の駿府出身の家臣たちが住んでいた地域です
・佃島 大阪佃村の漁師が入植して築いた島です
・代官町 代官などの屋敷が配置されていた地域です
・番町 下級武士(番衆)の長屋ができた地域です(小林 記)
季節は秋
漸く秋らしい風の到来で気持ちも和らいできました。季節も神無月です。神様の世界では、出雲の大社へ、日本全国の神様がご招待され、その御担当のエリアを報告し合い、またお互いの良き事例を学習し、国民(くにたみ)のため「神威を高める月」とされています。
古来より神様の世界では、マンネリに陥らず、常に新らしさを求めお力を高めておられる「神無月」は素晴らしいことと思っています。いずれにしても、これに倣い常に敬虔な気持ちでお互いを気遣い和やかに毎日を過ごしていきたいと思っています。
皆様におかれましては、この酷暑を乗り切りお元気でご活躍なされておられることとお慶び申し上げます。常日頃、「鎌倉楽しむ会」への心のこもったご協力とお気遣いをいただきありがとうございます。(清藤 記)
ご心配をおかけしました
8月20日に、過って自転車による交通被害で、頭を打ち、救急車で運ばれた博慈会記念総合病院(足立区)へ10年ぶりの検診で、MRI,CT、エコー検査など行いました。結果は後期高齢者の金属不良が、幾つか見つかり、従来の消化器内科から、あらたに心臓内科、耳鼻咽喉科などへの検査が始まり、それが12月まで続きます。
現在は、いつもと同じく生活はしていますが、病院検診が、検査日・結果診断日など9月から12月まで行い、部品の修理などがあるかもしれません。
そのような状態が到来したもので、8月下旬から、自分のことで精いっぱいでバタバタし、「鎌倉楽しむ会」の行事は、気にかけていたんですが延び延びになり大変申し訳ございません。
令和7年2月には、完全復帰できるように頑張りますので、ご迷惑をおかけしながら厚かましくもよろしくお願い申し上げます。
また、「足利尊氏のルーツ」の文章は、少しずつ進めていますので、完成しましたら発表したいと思っています。ご笑覧よろしくお願い申し上げます。
以上お詫びと勝手なお願いですが、お許しくださるように切にお願い申し上げます。
********************
お陰様で退院できました。経過は順調で、鼻洗浄三回が日課で、痛みも殆どありません。ラッキーです。
少しずつ無理なき活動をしていきたいと思っています。それには、紙上散策から始めてみようか?と思っています。
また、神社の方から「神仏混淆」について問われていますので、それについて書き込みしています。鎌倉会にも応用できれば、発表していきたいと思っています。
(清藤 記)